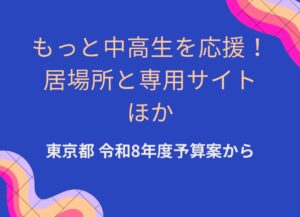いつもありがとうございます 都議会議員の高橋まきこ です。
子どもの事故予防地方議員連盟 にて、北海道におけるCDRモデル事業の取り組みをお聞かせいただきました。CDRは事故以外の病死なども広く対象としているものです。私は議連のほか、子ども虐待防止学会などへの参加を通じて、継続的にCDRを学び続けてきました。今回、直接行政の方からお取り組みを聞かせていただける、貴重な機会となりました。まずは北海道のみなさま、本当にありがとうございます。
◆CDR(Child Death Review:予防のためのこどもの死亡検証
こちらの高橋まきこブログ からお読みいただけたら
こども家庭庁CDRサイト
ポイントであり難しい点が「ご遺族の同意を得た検証の実施」です。その対象ケースの増大のために、まずはCDRが広く知られることが大切とされています。知らないことに同意をするには「学ぶ」時間がかかってしまうので、それによって同意までの時間も含むハードルが高いままになってしまいます。

【北海道のCDR】
R3年度に北海道医師会からの要望を受ける形で、直接北海道が事務局機能を担う形で、こども家庭庁のモデル事業に参画したそうです。実際に稼働したR4年度でしたが、コロナの影響も受けたとのことです。現在は協力医療機関数や事例把握件数が着実に伸びています。個別検証(詳しく調査する)対象も増やしていく道筋が立ってきたといったように受け止めました。CDRの大きな壁はご遺族の同意を得ることですが、これに対しては、信頼関係を深めるために赴くなど、手引きに準拠して、実施体制を構築しているそうです。
医療機関数
R3年度:9 → R6年度:30
北海道では
・直営(北海道保健福祉部の職員が事務局を担う)
・天使病院がワーキンググループ(WG)の中心
・北海道弁護士会 子どもの権利委員会がWGに参加
CDRで大切なことは予防策を策定して提言を行うところです。個別検証を増やしながら、提言にしっかりと結び付けていくことが重要で、期待されています。北海道では「予防策」と「提言」を区別した報告も検討されているそうです。

参考【東京都のCDR】
R5年度にモデル事業に参画し、R6年度に実質的な稼働が始まりました。東京都は福祉局が担当し、事業は日本総研に委託しています。委託しながらもどのように関係機関(現場)と直接的な連携を図っていくのか、は課題のひとつだと感じています。また、既に各部局で実施されている以下の4つのような検討の場と、CDRとして違いを明確にして実施するのか、その検証の重複はどう扱うのか、などを調整しながら、検証事例をいかにして増やしていくのかが課題だと思います。
1)東京都こどもセーフティプロジェクト(子どもの事故予防)
2)児童生徒の自殺防止サポート活動:5歳児から
3)教育・保育における死亡事故の検証(学校や保育所等)
4)児童虐待死亡ゼロを目指した支援(児童虐待死亡事例等検証部会報告書)
私個人の印象としては、既存の検討や検証の会議体等は活かして、それらからの連携という形で、総合的に個別検証や死亡小票の活用を検討する対象としていけないかと思いましたが、具体的には私自身が研究を深めたいと思っています。

【こども家庭庁と全国モデル】
こども家庭庁は来年度中にモデル事業を踏まえた全国展開へ向けて、取りまとめを行っていく予定とお聞きしています。同意や公判前資料の扱いや個人情報など、法的整備が国に求められている整理事項でもあります。国が示す手順が必要である一方で、都道府県によって病院や医師会などの考え方の違いや特性、成り立ちがあり、全国一律では進みにくくなることも想定されます。地域の実情に合った事業として、全国で検証事例が増え、子どもの死亡が減っていくように、その実現を願っています。



=== 区政と都政のさらなる連携へ === もっと区民の声を届けよう ===
中央区民のみなさまは 高橋まきこLINEオフィシャルアカウント から、直接感想をメッセージでお届けください。高橋まきこへのお問い合わせフォームや各種SNSのメッセージからも承っています。